需要の変化や急速に進化する技術からサステナビリティに対する責任、増大する利益に対するプレッシャーに至るまで、バリューチェーン全体を通じて企業もまた様々な課題に直面しています。ローランド・ベルガーは、このような課題をビジネスチャンスに変える支援をいたします。

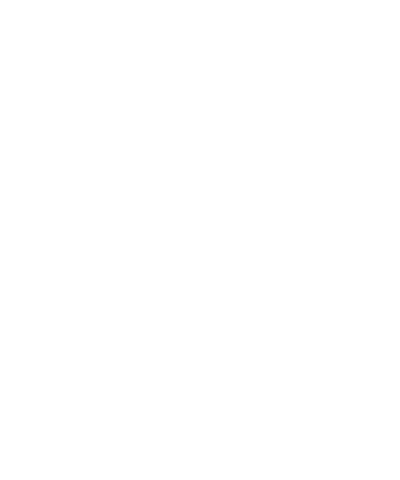
アジア圏におけるQコマースの可能性
筆者はバンコクに居住を置き、アジア各国における日系企業支援に従事している。ローカル消費者、並びに流通構造の変化に対する理解も深い。その日々のコンサルティング活動を通じて、今注目しているトピックのひとつがQコマース(クイックコマース)だ。本稿ではQコマースのプラットフォームビジネスとしてのポテンシャル、及びアジア圏内での普及可能性を取り上げる。
Qコマースの勃興
ここ最近、Qコマースという言葉をメディアでもよく目にするようになった。Qコマースを敢えて説明的に言い換えるならば「即時配達Eコマース」になるだろう。通常のEコマースが早くても数時間、場合によっては数日間デリバリーに要するところを10~20分で届ける。日本であれば近所のコンビニやスーパーに買いに行くのを、代わりに配達させるというコンセプトだ。
欧米等を中心に注目されている新たな流通形態であり、Gopuff 、Gorillas、Flink、Getir、Glovo等、多くのプレイヤーも登場している。手前味噌ながら筆者はコロナ禍以前からその普及に確信を持っていた。
そこからコロナ禍を経た2022年、ZホールディングスのQコマースへの本格参入も発表され、日本でもいよいよ熱を帯びてきたと感じる。
Qコマース成立要件とプラットフォームとしての可能性
このようなQコマースであるが、コロナ禍での外出制限がその需要は大きく後押ししたと言える。需要に呼応しようとするかたちで、供給側としてQコマースプロバイダーが増加しているというのが現状だ。
だが、Qコマース浸透におけるボトルネックは、しばらくは供給側であると筆者は考える。Qコマースに対する潜在需要は大きいものの、その要求水準は決して低くない。簡潔に言えば、「デリバリー時間」、「デリバリー価格」、「対応SKU数」、この基本的な要求を高い水準で満たす供給ができなければ、本当の意味での普及は難しいだろう(図表1)。

時間と価格は言わずもがなだが、対応SKU数、つまりはデリバリーできる商材の幅も重要なファクターになる。実際、弊社が実施した消費者アンケートでは、Qコマースで買いたい商品の幅は想像以上に広かった。
では、この3つを満たす供給体制はどのようなものか。シンプルではあるが、「配送拠点」と「配送車両(ドライバー含む)」の二つが閾値を超える規模に至ることだ。
配送する商品をストックしておき、そこからデリバリーするための配送拠点、そしてその商品を実際に消費者にまで届ける配送車両。前述の成立要件を満たし10~20分の即時配達を実現させるためにはこの二つが高密度で必要となってくる。
配送拠点が多ければ消費者までのデリバリー距離が短くなる。配送車両が多ければ「デリバリー待ち」の発生を防げる。結果、デリバリー時間は短縮される。
また、配送拠点数が増えることで、1配送拠点における1SKUあたりの在庫数を抑えられるため、逆にSKU数の増加が可能となる。より幅広い商品ラインナップを在庫できるというわけだ。
加えて、エリア内を動いている配送車両が増えることによって、それら車両に拠点ネットワーク全体での在庫最適化オペレーションに貢献させることもできるはずである。デリバリー稼働していない配送車両には、特定SKUの在庫数が減った拠点に別の拠点から商品を持ってこさせる。つまり、拠点間補充の役割を担わせるのだ。
更には、この高密度デリバリーネットワークがうまく稼働すれば当然ながら規模の経済が期待できる。そうすればデリバリー価格も最小化されるだろう。
それだけではない。Qコマースが秘める可能性は他にもある。日常的な購買で使われるようになれば、消費者が日々そこにアクセスするようなプラットフォームになっていくはずだ。集客が増えればプラットフォームビジネスとして、広告収入や消費データ販売等、新たなマネタイズソースも生まれてくる。
これはQコマースが従来のEコマース以上に、日常購買に使用され得るという特質を持つがゆえの可能性である。別のマネタイズソースが生まれれば必ずしもデリバリーフィーを取らなくてもいい。そして、デリバリーフィーが下がれば更に集客力も高まるという好循環に入るだろう。これがQコマースの持つ大きなポテンシャルである。
アジア圏におけるQコマース浸透の可能性
それでは、ここからはアジア圏におけるQコマースの普及可能性について論じたい。Qコマース成立要件である配送拠点と配送車両の密度をもとに検証する。

図表2は縦軸が、デリバリー車両(フードデリバリー向けバイク等)の都市部面積あたり数だ。この密度が高ければ、Qコマース向けの配達車両としても転用し得るポテンシャルがあると言える。ご覧の通り、アジア各国は高い配送車両密度を持つ。例えば、東南アジアではGrabやGojek等のライドへリングが浸透している点からもわかるところだろう。
横軸は食料品・日用品小売店舗の都市部面積あたり数であるが、こちらもアジア各国の密度は高い。伝統的小売がまだまだ数多く残ることに加え、近代的小売としてのコンビニの普及も進んでいる点が背景だ。一般的には、この密度が高いと需要面でQコマースが普及しづらいと言われている。コンビニや伝統的小売が数百メートル(場合によっては数十メートル)間隔で存在するのであれば、わざわざデリバリーさせるモチベーションが低いという見方だ。
果たして本当にそうであろうか。供給がQコマース成立のボトルネックとなる状況においては、筆者は必ずしもそうとは思っていない。
今、アジアにおいてコンビニ、スーパー、伝統的小売といった食料品・日用品小売店舗の在り方は大きく変わろうとしている。彼らが従来的な店舗販売ビジネスを守りたいのであれば、Qコマースは顧客満足向上のためのひとつのツールの位置付けで、そこで大きな売上を作ろうとはしないだろう。
だが、彼らの一部は自らの店舗ビジネスのディスラプトを手探りながら模索している。例えば、タイのCPグループ傘下のセブンイレブンは、デリバリーネットワークを強化し、Qコマースサービスの質・量向上に注力している。それに伴い、実店舗フォーマットの見直しも図っており、飲食スペースを充実させた店舗を増やしたり、小型キオスクに近い自動販売機の設置も増やしたりしている。
従来的なコンビニ店舗としての売上はQコマースに譲るかたちで、実店舗は別の価値提供を目指そうとしているのだ。彼らは店舗密度の高さを消費者のQコマース利用の阻害要因と捉えているのではない。逆に、店舗密度が高いゆえ、配送拠点の密度を高められるという発想に立っているのだ。
店舗密度の高さをQコマースに有効活用する事例はタイのセブンイレブンに限らない。近しい取り組みは、ベトナムのビンショップでも試みが為されている。また、インドではアマゾンやウォルマートといったオンライン・オフラインの大手小売が、伝統的小売であるキラナを配送拠点に活用しようしている。
このように、アジアでは高い小売店舗密度を利用して、Qコマースを根付かせようという動きが進んでいる。店舗密度が高いことを逆手にとって、供給側がチャネルの在り方を変えていけば消費者の需要は「買いに行く」よりも「運んでもらう」にシフトしていく可能性は充分存在するのではないだろうか。そして、Qコマースがアジア圏内で人々にとっての消費プラットフォームの基盤になる日も来るかもしれない。

